『ドリアン・グレイの肖像』とは?
概要
『ドリアン・グレイの肖像』は、アイルランドの小説家・劇作家オスカー・ワイルドさんの代表作かつ唯一の長編小説です。
ざっくりのあらすじ:自分は老いるのに肖像画は老いない、逆だったらいいのに!と強く願ったら本当にそうなる話。でもこの肖像画には恐ろしい秘密があって…
1890年版:中編
『ドリアン・グレイの肖像』は、アメリカの月刊誌『リッピンコット』にて中編小説の形で初出となりました。
しかし、ホモセクシュアリティーやその願望をほのめかす記載を含む、社会的に許されないと思われる記載を、編集者がオスカー・ワイルド本人の許可なく削除。
しかしながら、それでもヴィクトリア朝時代の道徳的価値観を害すこととなり、大きな議論と批判を巻き起こすこととなったようです。
1891年版:長編
この版では、ホモエロティックな記載が曖昧にされたり、画家バジル・ホールウォードの焦点が「(同性)愛」から「芸術」へ変更されました。
また、新たに複数の章も追加され、中編小説から長編小説の形へと進化。そして、有名な序文が加えられることとなります。
有名な序文
1891年版で追加された序文の目的は、前版への批判に対応し、自身の作品を守るためだったそうです。
この序文はそれ自体で有名になり、芸術家の権利や「芸術のための芸術(芸術至上主義)」を宣言するマニフェストとなりました。
『ドリアン・グレイの肖像』はどのように読まれるべきか、オスカー・ワイルドは格言の形で、社会における芸術家の役割、芸術の目的、そして美の価値を説明しました。
男色罪で有罪、そして投獄
1985年、オスカー・ワイルドは男色罪で有罪となり、1897年まで投獄されます。
裁判で『ドリアン・グレイの肖像』がやり玉にあげられ、本作の評判はさらに傷ついてしまったようです。
『ドリアン・グレイの肖像』のあらすじ
主人公のドリアン・グレイは若さと美貌を誇る青年モデルで、ドリアンの肖像画を友人の画家バジル・ホールウォードが完成させます。
そこへ快楽主義者のヘンリー・ウォットン卿が登場し、ドリアンの若さと美を讃美。自分は老いるのに肖像画は老いない、逆だったらいいのに!とドリアンは強く願います。
ヘンリー卿に感化されたドリアンは快楽主義を実践。背徳と享楽の生活を重ねる日々の中で、あるとき肖像画が老いていることに気づきます。どうやらこの肖像画は、罪を犯した分だけ老いるらしい。
怖くなったドリアンは肖像画を屋根裏部屋に隠し、自分だけの秘密にするが、画家のバジルがやって来て・・・
表面は快楽主義でコーティングされていますが、裏面は罪と罰(良心の呵責)や倫理の物語です。
『ドリアン・グレイの肖像』の感想・考察
日本語版と英語版を両方読んで感じたこと
日本語版は難解で高尚な文学という印象が強かったですが、英語版はそこまでの堅さは感じずエンタメ的に楽しめました。漢字の直角的、英語の曲線的デザインも影響してるのかもしれません。
『ドリアン・グレイの肖像』は、難解で高尚な文学感がある一方で、意外と平仮名も多いことに気づきました。
例えば、↓などは、普通なら漢字でもいいような気がしました。
わたし、ひとり、たち、いう、ひと、かれ、はいって…
もしかしたら翻訳者さんが意図的に漢字を減らして少しでも堅さを和らげようとしたのかも?(または、翻訳者さんの個人的なこだわり?)
●英単語は基本的なレベルのものが多い
日本語版から受ける印象とは異なり、英単語は基本的なレベルのものが多かったです。
このことから、逆説や警句はユーモアやスパイスとしてやってるだけで、全てがその内容をガチで主張しているわけではないように思いました(反証が簡単に見つかるものが多いため)。
『ドリアン・グレイの肖像』は、内容的に難しいので、意識的にエンタメ小説と思って読むくらいで丁度良いのかもしれません。
それぞれの逆説や警句に対して、本当にそうか?と疑うことで、考える練習にもなります。
※11章は例外。ここは単語、文構造、内容の全てから(悪い意味での)難解で高尚な文学感あり。ちゃんと読むの怠くてさっと飛ばしました・・・苦笑
●thatが多い
あとは、thatが多い印象も受けました。例えば、
I admit (that) I think (that) it is better to be beautiful than to be goodとか、
It was the strangest book (that) he had ever readとか、
省略可能なとこも省略しないできっちりthatと明記されています。
「ありがとう(ございます)」のように、言葉は省略しない方が丁寧ですから、thatをきっちり書くスタイルが、本作が醸し出す高尚な文学感の(全てではないけど)一端を担っているように思いました。
あくまで印象で、他作品と比較して数を数えた訳ではないですが、少なくとも『ドリアン・グレイの肖像』の英語版を読んだ限りでは、そのような印象を受けました。
難解な逆説や警句が多い、けど楽しい
『ドリアン・グレイの肖像』は、難しい逆説や警句が多くて分からない所もたくさんあるけど、それでも好きな作品です。すべてを完璧に分からなくても好きになっていいですよね。よく考えたら、大好きな作品でも分からないところは必ずあるので、すべてを分からなくても好きになれるのが文学の懐の深いところだと思います。
好きな箇所がたくさんあって選ぶのが難しいですが、以下に1つだけ引用して紹介します。
事物の本体を見きわめようとするならば、それに綱渡りを演じさせねばならない。真理が軽業師になったときはじめて、われわれはそれに判定を与えることができる。
何らかの意見なり主張があるとき、それを極論的な設定に置いてみて、それでも成立するかどうかで、真理を判断できるようになる、ということだと私は解釈しました。
昨今は「何を言うか」より「誰が言うか」が大事とされ、それもわからなくもないですが、やはり「誰が言うか」だけで判断したり、鵜呑みにするのはよくないことだと思います。
何らかの意見や主張があったときは、それに綱渡りをさせて真理を判断したいと思います。
序文のここが好き
有用なものを造ることは、その製作者がそのものを讃美しないかぎりにおいて赦される。無用なものを創ることは、本人がそれを熱烈に讃美する限りにおいてのみ赦される。すべて芸術はまったく無用である。
『ドリアン・グレイの肖像』の逆説の中では、これが特に好きです。芸術以外にも色々応用できると思います。
私のブログは無用だけど本人が楽しんでやってるので赦してください。
快楽主義・退廃主義を疑似体験
『ドリアン・グレイの肖像』のような快楽主義や退廃主義は、私は良心と臆病から自分では実行できません。
でも本を読むことで他人の人生を疑似体験できる(事実か創作かは重要じゃない)。しかも時間と空間を超えて。
これはよく言われる本を読むことの醍醐味で、『ドリアン・グレイの肖像』はその典型例だと思います。
登場人物の誰がオスカー・ワイルド?
個人的には、数々の逆説・警句でドリアン・グレイを悪の道へと誘惑するヘンリー・ウォットン卿かと思いましたが、
英語版Wikipediaにオスカー・ワイルドさん本人の言葉があったので、以下にメモします。
- バジル・ホールウォード:私が思う私
- ヘンリー・ウォットン卿:世間が思う私
- ドリアン・グレイ:私がなりたい私
逆説公ヘンリー・ウォットン卿のここが好き
Prince Paradox=逆説公ヘンリー・ウォットン卿が、会話中に雛菊をpluckしているところがとても好きです。
pluck:~を引き抜く、むしり取る、摘む、もぐ
会話に100%集中していない不誠実な感じ、花の命を○しても何とも思っていない悪役的なキャラ付けが、この仕草で上手く表現されていると思います(悪の組織の親玉が猫を撫でているのと似た設定?)
ちなみに、『ドリアン・グレイの肖像』でpluckが使われているのは以下の2回で、和訳版(新潮文庫版)はそれぞれ「摘む」「千切る」と訳されていました。
Load Henry smiled, and leaning down, pllucked a pink-petalled daisy from the grass 略
ヘンリー卿は微笑みを洩らし、背をかがめてピンク色の花弁をつけた雛菊を草のあいだから摘みとり~略 said the young lord, plucking another daisy.
ヘンリー卿は~雛菊を千切りながら答えた。
チェーホフの銃
誰も発砲することを考えもしないのであれば、弾を装填したライフルを舞台上に置いてはいけない。
これはロシアの劇作家アントン・チェーホフの言葉で、「ストーリーには無用の要素を盛り込んではいけない」と解釈されています。
『ドリアン・グレイの肖像』は、銃の代わりにナイフが登場します。
つまり、「舞台に銃があったら後で必ず発砲される説」のように、「小説にナイフがあったら後で必ず誰かが刺される説」というわけです。
これの似た例として、
- 2人がラブラブで周囲とあまりに温度差があったら後で必ず破局する。
- 「姉を不幸にしたら俺がお前を◯す」と弟が言ったら、後で姉は必ず不幸になるし、弟は必ず◯しにやってくる。
音楽のコードがV→Iに落ち着きたがるみたいな、重力のような法則、個人的には好きです。
犯した罪は取り消せない
ドリアンは、傷つけた彼女への謝罪の手紙を書き終えた時点で許されたと勝手に錯覚しますが、その頃すでに彼女は自◯していて取り返しがつきません。
ドリアンは、自分の罪は肖像画に表れるから心を入れ替えたら絵も元に戻るかと期待しますが、そうはならない。犯した罪は取り返しがつかない。
人間いつでもやり直せると言いますけど、それは加害者側の言い分であって、加害者が罰を受けたところで、被害者の傷は消えません。後で謝るくらいなら最初からやらないように、気を付けたいと思いました。
ダブリンの思い出:One City One Book

オスカー・ワイルドさんの出身地ダブリンは、毎年4月にダブリンに関係ある本をみんなで読もうというOne City One Bookをしています。
私がダブリンを訪れた2010年は『ドリアン・グレイの肖像』がその本で、街中にこのような旗があり、観光客の私にもダブリンの取り組みがすぐにわかりました。
街全体で読書を推奨するダブリン素敵です。





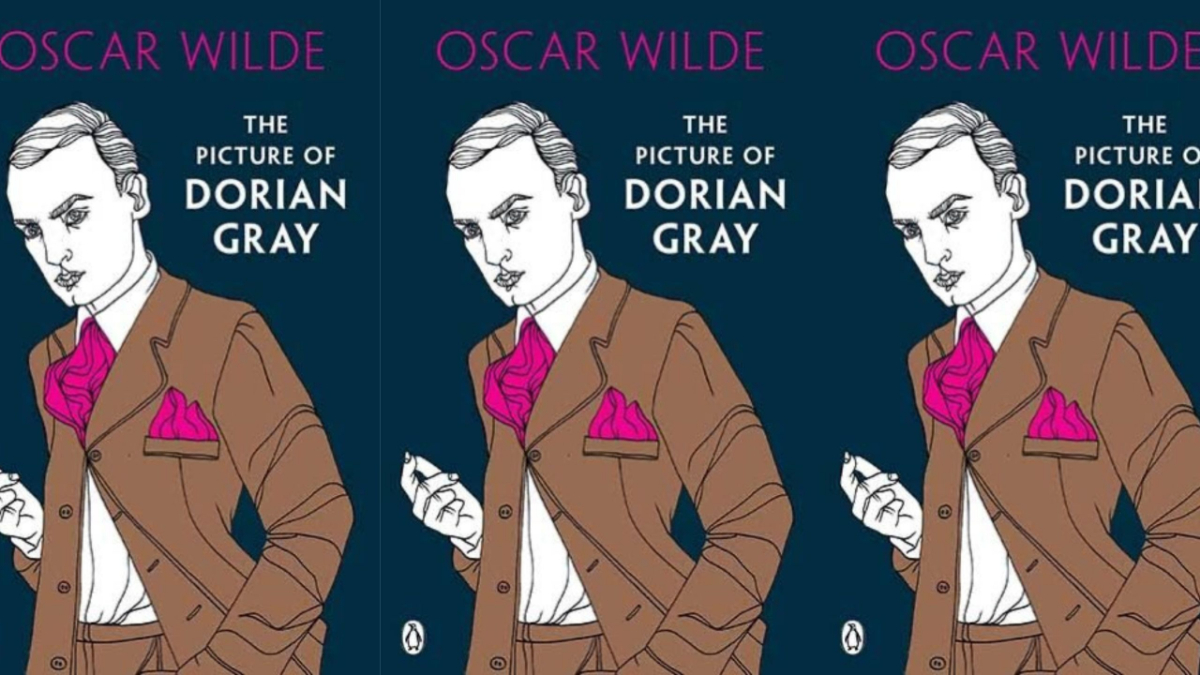




コメント