『ユリシーズ』とは?
『ユリシーズ』は、アイルランドの作家ジェイムズ・ジョイスが1922年に出版した、長編小説です。
本作は、作品はホメロスの叙事詩『オデュッセイア』を下敷きに、1904年6月16日のダブリンを描きます。
特徴は、文学の限界に挑戦するかの様に、文体は様々に変化することです。その結果、日常の細部が壮大な冒険へと転換される文学的実験作となっています。
20世紀最高の英語小説としても知られ、文学的評価は極めて高いです。しかし、おびただしい数の注釈や、英語文体のパスティーシュから成る第14挿話などが極めて難解なことから、多くの読者を苦しめています。
個人的には、読んでいて楽しいことと、文学的価値は分けて考える必要があるのかなと思っています。
『ユリシーズ』のあらすじ
全体のあらすじ
『ユリシーズ』は、1904年6月16日のダブリンでの一日を、三部構成で描きます。
第1部:まず、青年教師スティーヴン・ディーダラスが登場します。彼は塔での同居人との不和や母の死の記憶に苦しみつつ授業を行い、その後街をさまよい酒場へ向かいます。
第2部:並行して、広告業を営むユダヤ系の中年男レオポルド・ブルームの日常が描かれます。彼は朝食を整え、郵便で妻モリー宛ての情事の手紙を察知し、不倫を意識しながらも市内を歩き、葬儀に参列し、新聞社や酒場、浜辺を訪れます。
深夜、娼館で酩酊したスティーヴンが騒ぎを起こし警察沙汰となりますが、ブルームがスティーヴンを助け出します。
第3部:ブルームはスティーヴンを自宅へ招き入れて語り合います。ブルームは泊まって行くように勧めますが、スティーヴンは最終的に去って行きます。物語は妻モリーの内的独白で締めくくられ、彼女の欲望や記憶、夫婦関係への感情が流れるように展開し、平凡な一日が、冒険を語った神話の縮図として完結します。
挿話単位のあらすじ
●第1部:テレマキア(スティーヴン・ディーダラス)
第1挿話:テレマコス – サンディコーヴの塔で、スティーヴンは友人のバック・マリガンとイギリス人ハインズと同居しています。死に際の母の祈りを拒んだ罪悪感に苦しみ、仲間からも疎外されていると感じます。
第2挿話:ネストル – スティーヴンは学校で授業を行い、その後、校長ディージーと歴史や運命について議論します。ディージーから新聞に投稿する論文を託されます。
第3挿話:プロテウス – スティーヴンは海辺を歩き、哲学的な思索や記憶に耽ります。孤独や内面的苦悩が浮かび上がります。
●第2部:オデュッセイア(レオポルド・ブルーム)
第4挿話:カリュプソ – ユダヤ系中年男性の広告取りレオポルド・ブルームは、妻モリーに朝食を用意します。彼女はこの日、不倫相手のボイランを迎える予定であり、ブルームはそれを感じ取ります。
第5挿話:食蓮人たち – ブルームは用事をこなし、郵便局で秘密の女性との文通の手紙を受け取ります。日常の細事にも思索を重ねますd。
第6挿話:ハデス – ブルームは友人たちと馬車に乗り、パディ・ディグナムの葬儀に参列します。死や宗教について語られ、彼の孤立した立場が浮き彫りになります。
第7挿話:アイオロス – ブルームは新聞の広告を取ろうと試みますが軽んじられます。ここでスティーヴンも一瞬現れ、ディージーの論文を新聞社に渡します。
第8挿話:ライストリュゴネス族 – ブルームは酒場で一人昼食をとり、人々の食欲を眺めつつ人生や死について考える。孤独感が際立つ。
第9挿話:スキュレとカリュブディス – スティーヴンは国立図書館で『ハムレット』の持論を文学者達に語ります。ブルームも通りかかるが目立たちません。
第10挿話:さまよう岩々 –ダブリン市民の日常を19の短い場面で描きます。時空が一致する場合は、それぞれの視点が交錯します。ブルームはモリーへの本を買います。
第11挿話:セイレン – ブルームは妻モリ―の不倫相手ボイランを目にし、離れて観察しながら苦悩します。ブルームは酒場で歌声を聴いています。d
第12挿話:キュクロプス – ブルームはパブで排他的なナショナリスト「市民」と口論になります。ユダヤ人であることを嘲られますが、普遍的な愛で反論します。
第13挿話:ナウシカア – ブルームは砂浜で若い女性ガーティを見つめ、彼女の挑発的な仕草に興奮し自慰に至ります。羞恥と解放感が交錯します。
第14挿話:太陽の牛 – ブルームは知人の見舞いで産院に行きます。そこではスティーヴンやその仲間がいて、一緒に酒を酌み交わします。この挿話全体は英文学史の文体を模倣する形で展開します。
第15挿話:キルケ – ブルームとスティーヴンは売春宿で幻想的で悪夢的な幻覚を体験します。スティーヴンはシャンデリアを壊し、逃げ出した後、イギリス兵に殴られ、警察沙汰となりますが、ブルームに救われます。
●第3部:ノストス
第16挿話:エウマイオス – 疲れ切ったブルームとスティーヴンは御者小屋で休み、地元の人々と会話しいます。二人の間に父子のような絆が芽生えます。
第17挿話:イタカ – ブルームはスティーヴンを自宅に招き入れ語り合います。やがて2人は裏庭で星空を見上げながら放尿します。スティーヴンは宿泊の勧めを断り、去って行きます。
第18挿話:ペネロペイア – ベッドに横たわるモリーの独白という形で、過去の記憶や欲望、夫との関係、不倫への思いが流れるように綴られます。最後はブルームからのプロポーズの記憶と共に、誰もが知っている肯定的な言葉で終わります。
『ユリシーズ』の感想・考察
第1部:テレマキア
第1挿話:テレマコス
めちゃくちゃ面白い。もちろん注釈がないと、いや、あっても理解できないところは沢山ある。それでも面白いのは、まず『若い芸術家の肖像』の既読者にとって俺達のスティーブン・ディーダラスが登場すること。そして、主役を完全に食っている悪役のマリガン。嫌な奴だけど存在感抜群。特に鳥の真似をして歌った一行「空を飛ぶのは血筋のせいさ」が最高(What’s bred in the bone cannot fail me to fly.)。本当にぶっ刺さる一行があれば、極論それだけでその作品を好きになる理由になる。
活字だけだとわかりにくいけれど、オーディブルを聴くとテンポのよい喜劇的雰囲気が伝わってきて楽しい。マリガンは陽キャ、スティーヴンは陰キャ。
「Usurper.」は本章の最後に印象的な幕を下ろすスティーブンの心の声(自由間接話法)。オーディブルは憎しみを込めた小声で読まれていた。日本語版は「王位を奪うやつ」となっているけど、個人的には「(王位)簒奪者め」という印象を受けた。
📝メモ
●スティーヴンはハムレットやテレマコスの子孫(苦悩する、父がいない、親を簒奪される)。
●スティーヴンは『若い芸術家の肖像』で「I will not serve」「I will not serve that in which I no longer believe, whether it call itself my home, my father land, or my church: and I will try to express myself in some mode of life or art as freely as I can and as wholly as I can, using for my defence the only arms I allow myself to use – silence, exile, and cunning」と言っていたが、『ユリシーズ』では「I am the servant of two masters, Stephen said, and English and an Italian.」
●「You (Stephen) have g.p.i. 略. General paralysis of the insane.」。paralysis(中風)は『ダブリナーズ』のテーマを引き継いでいる。
第2挿話:ネストル
教師のスティーヴンさん、学校に遅刻した疑いがあって草(本文に明記はないが、状況的にそう推理できるらしい)。やる気のない教師、出来の悪い生徒、物知り顔で間違ったことを言う校長。本章の登場人物は駄目な人間ばかり。だがそれがいい。落語みたいに人間の弱さを肯定したい。
『オデュッセイア』でテレマコスが「You are going to be a great hero someday.」と言われたことを思い出す。『ユリシーズ』でスティーヴンは「I am not a hero.」と言う。この対比が凄くいい。
※本当は歴史やユダヤ人の話がメインなんだろうけど、今はそういう気分じゃなかった。
「Futility.」はスティーヴンが出来の悪い生徒に教えてるときの心の声(自由間接話法)。日本語訳は「空しい仕事」で意味は合ってるけど、オーディブルを聴いた感じだと「くだらねぇ」。多少の怒りと自虐も入っているかも?私も仕事中に全く同じように思ったことがあるので、とてもよく分かった。
📝メモ
●I fear those big words, Stephen said, which make us so unhappy.
※Big words = generous=寛大, just=公正
●History, Stephen said, is a nightmare from which I am trying to awake.
●You were not born to be a teacher, I think. Perhaps I am wrong.
A learner rather, Stephen said.
●前章でスティーヴンの給料は4ポンドと言っていたはずだが、本章で受け取るのは3.6ポンド。スティーヴンは頭は良い設定なので、学校側がちゃんと支払えていない?
第3挿話:プロテウス
海岸を歩くスティーヴンの独白。前章までとは文体が明確に変わりとても難解。はっきり言って苦痛だったけど初読者が最も挫折しやすく、ジョイス研究家が一生を懸けて取り組むレベルと知って安心した。とても示唆的に書かれてはいるとは思う。でもここは飛ばしてもよさそう。完走という大きな目的のためには、小さいことを切り捨てることも必要だから。
本章は難解過ぎて活字を読むのが苦痛だったけど、オーディブルを聴くのは楽しかった。この翻訳はオーディブルがない時代のもの。私なんか英語力も知識も翻訳者さんの足元にも及ばないのに、一聴しただけ一気に視界が開ける。「百読は一聴にしかず」。音にはそれくらい豊かな情報が含まれている。苦痛なほど難解な本章だからこそ、それがとてもわかりやすく感じられた。
活字本の強みはそもそも情報の保存及び複製、並びに携帯性だったはずで、感情やニュアンスを含めた情報伝達力はむしろ弱み。活字読書は、音楽を聴かずに楽譜を読むことに似ているのかも。音がないと情報伝達力はめちゃくちゃ下がる。人間も動物だから声という野性的ツールの方が多くの情報を伝えられるのだろう。活字本とオーディブルを目的によって使い分けれると良いと思う。
第2部:ユリシーズの放浪
第4挿話:カリュプソ
第1挿話と同時刻のエクルズ通り7番地。ここで真の主人公ブルームが登場。妻モリ―に不倫の疑いがあるが、夫ブルームは敢えて踏み込まない。ベッドで寝ている妻に朝食を作ってあげるヨキダンである。今日もさわやかに麗しく生きていきましょう。
📝メモ
●文体:第1挿話と同じ三人称の語りに戻るが、この第4挿話の方が自由間接話法の割合が顕著に多い。
●キーワード:Metempsychosisは神話との対応を示唆か。
●スティーヴンとブルームの対比
スティーヴン
知識:豊富
思考:鳥の様に自由
性格:複雑、陰キャ、悲劇的
好きな食べ物:不明
ブルーム
知識:不足
思考:犬の様に限定的
性格:単純、陰キャ、喜劇的
好きな食べ物:羊の腎臓
●スティーヴンの遅刻の疑い
第1挿話最後のラテン語の祈り(3行で記載)と第4挿話最後の鐘の音(3行で記載)(8:45am)が同時刻として対応していると思われる→マーテロー塔から学校まで徒歩で15-20分→9時始業なら遅刻の可能性大(良くてギリギリ)
第5挿話:食蓮人たち
第2挿話と対応してこちらも駄目な人間ばかり登場。ブルームは知人の葬儀に参加する前にダブリン市内での所要を済ます。スティーヴンと同じく会話中に心の声が挿入される(自由間接話法)。目の前の相手に集中していないテキトークである。
本挿話は、ラ・チ・ダレム(モーツァルト)のハミング、妻に秘密にしている文通、スウィニー薬局(レモンの香りのする石鹸、オレンジウォーターの香水)、競馬予想のヒント、トルコ風呂などネタが多い。
その中でも特筆したいのはカトリック教会でのミサで、理由は教会批判が痛烈だったから。前挿話の猫がミルクをペロペロ舐めるシーンは、教会と信者への当て付けだった。ラテン語を使えば信者は理解できず思考停止してしまうという指摘は、ダブリナーズの主題paralysis(中風)に通じる。ブルームはミサの作法が分からない。周囲の見よう見まねで起立、着席する様が笑える。
📝メモ
●I will risk it, said he. 思い切ってやってみるよ、と彼は言った。
原文のriskがとても良かった。この世界は安全圏にいるまま良い思いができるようにはできていない。
第6挿話:ハデス
ブルームは故人の自宅から墓地へ、葬儀参列者達と共に馬車に乗る。その道中、馬車から見える景色を通して、ダブリン市内が描写されていく。『ダブリナーズ』達も続々登場。ジョイスの言葉「たとえダブリンが滅んでも、『ユリシーズ』があれば再現できる」の一端を見た。
第6挿話は、三人称の語りが増え、自由間接話法が減る。この塩梅は第1挿話に似ている(さらに言うと、ブルームとスティーヴンはどちらも他人と一緒にいるが、心は孤独を感じている)。第1〜6挿話の構造はABCCBAで、これにて序盤の一区切りか。ここまでで全体の15%。
📝メモ
●繰り返し使われる言葉
Retrospective arrangement
意味:過去を振り返って、整理し直す
初出:第6挿話
検索ヒット数:7回
※sort of, kind of を伴う形も含む:Retrospective (sort/kind of) arrangement
『ユリシーズ』は難解なので、初読時に全てを理解することはできない。何度も再読することで徐々に理解が深まり、楽しめるようになる。作者からのメッセージかもしれない。
Metempsychosis
意味:輪廻転生
初出:第4挿話
検索ヒット数:11回
最初は神話との対応を示唆する言葉かと思った。それもあるかもしれないが、主要な意図はRetrospective arrangementと繋がっている気がしてきた。つまり、輪廻転生とは、何度も再読すること。
毎日繰り返される1日にも適用できそうだ。毎日生まれ変わったかのように新鮮な気持ちで生きれたら、『ユリシーズ』を解読するように真剣に生きれたら、再読で理解が深まるように素敵に歳を重ねて行けたら。実際にやるのは難しいけれど、理想としてはこうありたい。
Voglio (e non vorrei)
意味:行きたいけれど行きたくもなし
初出:第4挿話
検索ヒット数:9回
モーツァルト『ドン・ジョバンニ』内の二重唱『お手をどうぞ(La ci darem la mano)』の歌詞。正しくはVorrei e non vorrei(行きたくもあり行きたくもなし)。ブルームは勘違いしている。いずれにしてもorではなくandであることが重要だと思う。
英雄のオデュッセウスに対して、凡人のブルーム。両方英雄(orで片方を選択/片方に統一)だと解釈が限定されてしまうが、英雄と凡人(and)ならその心配はない。相反する二重性が永遠性を生む。『ユリシーズ』に永遠性を与えるためにはorではなくandが適している。
orのどちらかに決断できない様は、『ダブリナーズ』の主要テーマparalysis(中風)に通じる。
そういえば、妻に朝食を用意してあげる夫は、当時は特に珍しく、女性性を持った男性と言えるかもしれない。男or女ではなく、男and女。二重性。
To be or not to be(生きるべきか死ぬべきか)ではなく、To be and not to be(生きるべきであり、死ぬべきでもある)。意味が分からない。だから延々と考え続けることができる。
第7挿話:アイオロス
舞台を新聞社に移し、鳥の目を持つ語り手がダブリンをより広範囲に描写していく。短い断章の集まりで構成され、それぞれに新聞の様な見出しが付く文体が真新しい。小説とは何か?ジョイスは小説の限界を広げて行く。肝心の内容は難解でよくわからない。
スティーヴンが披露する自作の寓話は、ちゃんと仕上げれば『ダブリナーズ』に収録できそう。「You can do it. I see it in your face.」
第2挿話と同じく、歴史は悪夢という位置付け。繰り返し言われると、そんな気がしてくる。「Nighmare from which you will never awake.」
新聞社に勤めるブルームは広告の契約を獲ろうとする。スティーヴンは校長に依頼された論文を持ってくる。二人はまだ出会わない。
シルヴィア・ビーチは『ユリシーズ』のことを「文明のおぞましい側面に反逆する記録」と書いていたことと、何か関係があるのだろうか。
第1-9挿話の執筆時期が第一次世界大戦(1914-1918年)とほぼ一致していることは、どれくらい影響しているのだろう?
📝メモ
●第7挿話アイオロスはジョイス本人が朗読した録音が残っている。
ジョイスは、イオラスの挿話に出てくる演説を選びました。これが『ユリシーズ』から抜き出すことのできる唯一の一節であり、「雄弁」であり、したがって朗読に適した唯一の一節であるとも彼は言いました。
私は、彼がイオラスからのこの一節を選んだのは、それが雄弁だという理由だけによるものではないと考えております。この一節は、彼が彼自身の声で発言し保存してもらいたいと願ったなにかを表していたと私は信じます。「それについて彼は大胆に一段と声を張り上げていった」―と、レコードが響き始めるように、これは単なる雄弁以上のものであると感じられます。
『ユリシーズ』のレコードを聴きたい人は誰でも、パリにある「声の博物館」で聞くことができます。ここには、カリフォルニア州出身の私の友人フィリアス・ラランの忠告のお陰で、ジョイスの朗読が、幾人かの偉大なフランスの作家たちに混じって、保存されております。
第8挿話:ライストリュゴネス族
再びお馴染みの文体(自由間接話法)に戻り、ブルームはリフィー川の北岸から南岸へと歩く。オコンネル通り、オコンネル橋、ウエストランドモア通り、グラフトン通り。地図その足取りを追うと、ダブリンに飲み込まれ、その食道を下っているみたいだ。ブルームは決して羽目を外さない。穏やかだが退屈な人。妻の不倫相手を見かけ、動揺し、逃げ隠れる。
ブルームが遅めのランチを摂るデイビー・バーンズはダブリンの胃だ。ブルームが飲食した赤ワイン(バルガンディー)とゴルゴンゾーラチーズのサンドウィッチは、観光アトラクションになっている。メニュー上の正確な名前は忘れてしまったけれど、「ユリシーズのブルームと同じやつ」で通じる。

デイビー・バーンズ
第9挿話:スキュレとカリュブディス
スティーヴンは国立図書館で文学者達を相手にハムレット論を語る。アイルランドにはハムレットの様なアイコン的キャラクターや『オデュッセイア』の様な国民的叙事詩がまだない。本挿話は勇敢にも「ブルームと『ユリシーズ』がそれになる」と名乗りを上げているかのよう。ジェイムズ・ジョイスは『若い芸術家の肖像』で飛ぶ決意をして、『ユリシーズ』で実際に飛んだ。その飛行は成功し、ジェイムズ・ジョイスは『ユリシーズ』で文学のパンテオン入りを果たす。
オデュッセウスは英雄だけど、ブルームは英雄じゃない。英雄が必要な時代は不幸な時代。ユリシーズ第1~9挿話の執筆時期は第一次世界大戦(1914~1918年)とほぼ一致。作者なりの反戦の意思表示?
📝メモ
●シェイクスピア・アンド・カンパニイ書店のシルヴィア・ビーチ「これ(ユリシーズ)は文明のおぞましい側面に反逆する記録であり、真実に溢れた記録でもあります」
●第9挿話は全体の中でも特に難所の一つで、本文1ページ当たりの注釈ページ数は第3位(第1位は第3挿話)。ここで諦めてはいけない。スティーヴンのハムレット論の概要は、日本語版に要約があるから心配ない(ガチ勢以外は深入りしなくていいと思う)。本挿話で最も重要なことは、ジェイムズ・ジョイスが文学のパンテオン入りに名乗りを上げたことだと思う。
●ジョイスの教会批判:the church is founded and founded irremovably because founded, like the world, macro-and microcosm, upon the void. Upon incertitude, upon unlikelihood.
第10挿話:さまよう岩々
短編集『ダブリナーズ』の簡易版の様な19の断章。ダブリン各地を異なる主役を用いて描写していく。各章は互いに入り組み、時空が一致するところはキュビズムや後の『アレクサンドリア四重奏』を想わせる。ダブリンが滅びても『ユリシーズ』があれば再現できる。
いずれも平凡な日常で、特に何が起こるというわけでもない。全18挿話のほぼ半分の位置にあることから、前半と後半を分ける幕間の様な印象。『ユリシーズ』は難解だから、一休みできて助かる。好き。
📝メモ
●ここまでで33%、10/18挿話、時刻は4pm。
●「Misery! Misery!」:ジョイスの描くダブリナーズ=ダブリンのレ・ミゼラブル達。羽振りがいいのは後にブルームの妻を寝取るボイランくらい。悪役の設定は完璧。
第11挿話:セイレン
音の似た言葉やオノマトペで遊ぶ音楽的な挿話。Begin! ブルームは妻モリーの不倫相手ボイランをまた見かけ、今度は離れて観察する。約束の4pmになっても彼は行かない。わざと遅れて焦らすつもりか?そんなこと優しいブルームにはとてもできない。Done.
『ユリシーズ』が平凡な日常を描く理由の一つは反戦なのだと思う。第一次世界大戦(1914~1918年)が始まった1914年に執筆を開始、終戦後の1918年〜1920年に一部連載、1922年に出版。戦争という文脈に置くと平凡な日常は反戦の意味を帯びる。
📝メモ
●マルセル・デュシャンのレディメイドみたいだ。レディ・メイドは最初に『自転車の車輪』が1913年にあり、有名な『泉』は1917年。時期的にも一致する。
①自転車の車輪、1913年
②泉、1917年

●ConqueringとUnconquered
①悪役ボイランは征服する英雄
古いタイプ。例えば、オスマン帝国の征服王メフメト二世。
②主人公ブルームは征服されない英雄
新しいタイプ。例えば、非暴力不服従のガンジー。
ガンジーとは時代が一部重なるけど、どれくらい関係しているんだろう?
第12挿話:キュクロプス

飲酒はアイルランドの呪い(『ダブリナーズ』や『若い芸術家の肖像』から一貫)。今回はパブを舞台に、ユダヤ人のブルームが愛国主義者(綽名は市民)と口論をする。力、憎しみ、歴史。アイルランド人の資格。歴史という悪夢はいつ終わるのか?
市民は単眼の巨人キュクロプスと対応。誇張された表現が面白い。名前はおそらく『オデュッセイア』の「Nobody」に由来。排外主義を担当。「We’ll put force against force, says the citizen.」
ブルームはキリストを担当(非暴力不服従)。妻を寝取られても何もしない。市民の憎しみには愛で反論(手は出さないが口は出す)。隣人を愛せ。名前の意味は「花」。「Love, says Bloom. I mean the opposite of hatred.」
本挿話の語り手は謎のI(おれ)で、今までの全知の語り手+ブルームの自由間接話法ではない。その理由を考えていてひらめいた。ジェイムズ・ジョイスや『ユリシーズ』の核心に迫る重要事項だと思う。
前提:『ユリシーズ』が平凡な1日を描く最大の理由はおそらくエピファニー及び/又は聖体変化。エピファニーとは、ある種のひらめき/天啓のことで、代表例は大天使ガブリエルからの受胎告知。聖体変化とは、ただのパンとワインがキリストの肉と血に変化する体のこと。つまり、平凡が特別に変化すること。
平凡の中に特別を見つけ(ひらめき)、それを形にするのが芸術家の仕事。だから『ユリシーズ』の物語自体は平凡な1日にして、その中に様々な意味を隠した。『ユリシーズ』は謎解きゲーム、又は、エピファニー/聖体変化を練習する場。
結論:第12挿話のブルームはキリストに重なる。ブルームにキリストが宿り聖体変化が起こったという体なのだと思う。この場合、ブルームはパンやワインと同じ客体でなければならない。今までのような自由間接話法(主体)は使えない。ブルームの客体化だけなら今までと同じ全知の語り手でもいいが、それだと特別感がない。他の挿話と明確に差別化するために、新たな語り手I(おれ)が必要だった。こう考えると辻褄が合う気がする。
●文明のおぞましい側面に反逆する記録
「私は連載の形になっているいくつかの『ユリシーズ』の断片を読みました。これは文明のおぞましい側面に反逆する記録であり、真実に溢れた記録でもあります。」
→上記は、第12挿話のことのような気がした。一言に要約すると、歴史は悪夢。それ以外には考えにくい。
歴史は悪夢。最初はユダヤ人のこと、他人事と思っていたけど、日本もだった。どの歴史が正しいかはさておき、中国、韓国との関係は未だに目覚めれない悪夢の様だ。台湾や香港の人々にしたら、中国との関係。ドイツのナチス。他にも私が知らないだけで、多くの国に未だに目覚めれない悪夢がありそう。
自国の歴史からは、良し悪し関係なく、へーそうなんだと学ぶだけで、誇りに思える/思えないを決めるのは今の状態がどうかだと思う。仮に栄光の歴史でも、それを理由にした誇りならダサい(過去の栄光おじさん)。この歴史は誤りだから訂正したい→わかる。〜誇りに思えないから訂正したい→わからん。
●―Who made those allegations? Says Alf. ―I, says Joe. I’m the alligator.
真剣な議論をしているときに、しょうもない駄洒落をぶっこんで来るの草。
●Ireland sober is Ireland free. 禁酒アイルランドは自由アイルランド。
●One of those mixed middlings he is.
両性まぜこぜの中性(p386)。ブルームは男性性と女性性を併せ持つ中性(orではなくand)。
第13挿話:ナウシカア
英語圏で禁書になる主な原因を作った問題の回。ブルームは前回はキリストが宿ったかの様だったが、今回はとんでもない変態に。ただ、表現は婉曲的で、禁書にするほどのことなのかは疑問。私には理解できない宗教的価値観が関係しているのかも?
ジョイスは『ダブリナーズ』の頃から一貫して宗教(というか教会のやり方?)に否定的で『ユリシーズ』では特に厳しく批判。こっちも反感を買う原因になってそう。
「消すと増える」に似て「禁書にされると読みたくなる」。『ユリシーズ』は禁書で得をしている。
📝メモ
●ここまでで50%、13/18挿話、時刻は9pm
●下記参考文献に以下の記載あり:Nothing happened between them (Gerty and Bloom), he (Joyce) replied. It all took place in Bloom’s imagination.
第14挿話:太陽神の牛
英語文体のパスティーシュから成る最大の難所。物語は、ブルームが難産で苦しむ知人を見舞いに行くところ。妊娠から出産に向かって、英語の文体が古代から現代へと発達していく。作者が千時間かけた力作らしいが、読者にとってはただの地獄だった。
ところが、文体の発達に伴い少しずつ光が射してきて、19世紀ディケンズの文体でようやく快適に読めるようになる。ここは長く苦しかった出産が終わって幸せなところ。今までの地獄の苦しみは、出産の苦しみに対応させた意図的なものだったのか!それに気づいたとき感動した。全ての人間は母親が苦しみに耐えた結果生まれる。母親すごい。
●英語文体の発達に沿った感想
冒頭は呪文、祈り、叫び。呪文はアイルランド語、英語、ラテン語の混成で、響きが先史時代を想わせる(混成は生命誕生前の原始スープみたいでもある)。祈りは産婦人科病院の院長を神に見立てて。叫びは喜びの間投詞で、子供や文字の誕生と対応しているか。
いすれも活字だと分かりにくいが、音で聴くとよく分かる。活字は理性で摂取するもの、音は野性で感じるもの。ここは意味理解より感じることが重要だと思う。Don’t think, feel! 冒頭の呪文、祈り、叫び。この部分は最高。
次はラテン語からの直訳(言葉遣いや構文の英語化なしの直訳らしい)。しかも一文が長く、たった二文で一頁に及ぶ長さ。文体に加え内容も難解で、ここで心を折られた。
その後も英語史に沿って文体が発達していくが、全く意味が分からない。地獄。日本語訳を読んでも意味不明。読んでいて苦痛。
18世紀頃になると少しずつつ文体が現代英語に近づいてくる。でも古い単語は分からないし、内容が難解で、引き続き地獄。英語ネイティブも同じ感想だと思う。
19世紀ディケンズの文体でようやく快適に読めるようになる。ここは長く苦しかった出産が終わって幸せなところ。今までの地獄の苦しみは、出産の苦しみに対応させた意図的なものだったのか!それに気付いて感動した。全ての人間は母親が苦しみに耐えた結果生まれる。母親すごい。
このまま最後まで行けるかと期待していたら、最後は文体が崩壊。方言、隠語、アイルランド語のごちゃ混ぜで、全く意味不明。地獄アゲイン。
本挿話はとても感動的に書かれていると思う。でも『ユリシーズ』を再読するとき、ここは飛ばすことになるだろう🤣
第15挿話:キルケ
戯曲形式の文体と、全体の9割を幻覚が占める幻想性が特徴の回。事実上全ての既出キャラ、モノ、トピックがミキサーにかけられた上で再登場し、作品全体に蜘蛛の糸の様な相互関係が形成される(何世紀も忙しくなることが確定している教授達を更に忙しくさせることに)。
多くの批評家が最も優れた部分を評しているらしいが、読者的にはよく分からない回だと思う。もっとも、幻想を楽しめばよくて、合理的に理解する必要はないのかもしれないけれど。
戯曲体だからか、ふざけている部分も少なくないと思う。ブルームサレム(ブルーム+エルサレム)の王になるのは草。性転換したり、SMの女王様の馬になったり、もう滅茶苦茶である。辞書にない言葉(今回に限らないが)や、英語をフランス語の構文に当てはめたところは、特にわかりにくい。言葉や小説の限界突破に挑んでいるかの様。
物語的には、ブルームがスティーヴンを追いかけて欧州最悪のスラムにある娼婦館にやって来るところ。2人が見る幻覚は主に過去が原因。History to blame. ジョイスは歴史に対して一貫してネガティブ。確かに、歴史は碌なものじゃない。いや、人間が歴史を悪用しているだけか。人間の問題は全て人間が作ったもの。解決できるのもまた人間。
『ユリシーズ』中最大の回で、第1~8挿話までの合計と同じくらい、2位とダブルスコア以上、ここだけで長編小説1冊分の長さ。
📝メモ
彼は、普通の描写で描かれた人物はあらゆるものが描き落されていると考えていました。言語に関しては、英語の語彙はこれ以上言語を創らなくても十分過ぎると考えていたショウと、ジョイスでは意見が一致しませんでした。ジョイスは、言葉のゲームで人々が望むあらゆる楽しみを味わうという考え方であり、彼には言葉に限界を設けなくてはならないという理由がわからなかったのです。つまり、フランス人の理解しているmesure(節度)というものは、『ユリシーズ』の創造者、特に『フィネガンズ・ウェイク』の創造者の性格とは一致しなかったのです。
ジョイスが彼の新しい作品(『フィネガンズ・ウェイク』)にとり掛かった当時、イギリスでみられた傾向は、英語を一定の範囲内に止めようとすることでした。
第3部:ノストス
第16挿話:エウマイオス
日付も変わり午前1時。ブルームは夜の街からスティーヴンを救出し、馭者溜まりの喫茶店へ連れて行く。しかし、2人の波長は合わず、会話を主導するブルームに対し、スティーヴンの反応はそっけない(欠伸もする)。
今回はブルームへのトリビュートで、もしブルームが書くなら、という設定。主人公のブルームはそれに値すると思うけど、とんでもない悪文に辟易する。この書き手いや(わざと悪文を書くジョイスが上手い)。
具体的には、まず、一文が1/2頁あったり、酷いときは1頁近くあったりで、滅茶苦茶読みにくい。どれだけ長い一文を書けるか選手権かよ。文中への挿入句も多く、主文が分断されて読みにくい。次に、慣用句の使用が多くて寒い。once in a blue moonとか要らんし、こういうのが美文と思っているブルームはセンスない(という設定)。最後に、副詞が多いのも未熟な書き手の証。過剰な修飾は悪文の典型(そういえば第一挿話も副詞が多く、~ly ~lyうるさかった)。スティーヴンが欠伸する気持ちわかる。
ブルームの下記主張は作者の主張を代弁しているように思う。
I resent violence or intolerance in any shape or form. It never reaches anything or stops anything.
第17挿話:イタケ
ブルームの自宅で語り合った後、スティーヴンは夜のダブリンへ去って行く。スティーヴンのその後は記載がないが、やがて『ユリシーズ』を書くと思いたい。「ぼくの族のまだ創られていない意識を、ぼくの魂の鍛冶場で鍛えるために。」「古代の父よ、古代の芸術家よ、永遠に力を与えたまえ。」やっぱ、スティーヴンよ。
ブルームはベッドに妻の不倫の痕跡を認めるが許す。復讐する?否。「悪に悪を重ねても善は生まれないから(as two wrongs did not make one right)」妻への求婚者達を皆殺しにするオデュッセウスとは真逆。ジョイスは古い英雄を新しく作り変えた。悪に悪を重ねる負の連鎖を終わらせよう。『ユリシーズ』の内容面では、これが作者の最大のメッセージのような気がした。
文体は全知の語り手による問答形式と、具体的にひたすら列挙して行くスタイル(例えば引き出しの中に入っている物)が特徴的な回。前者は『神曲』天国篇を、後者は『イリアス』で両軍の戦力をひたすら列挙していく回のオマージュか。文字の始原となった帳簿まである。終わりから始まりへ戻っているかの様だ。それは新しい始まりのため?
『イリアス』で両軍の戦力をひたすら列挙していく回を思い出した。ただの列挙なら怠いけど、故人の形見を慈しんでいると思うと一つ一つがかけがえのないものとして輝き出す。細部の背景に無限を感じた。これは千利休の待庵だ。カテドラルがどれだけ大きくとも限界はすぐに来る。無限を実現できるのは想像の中だけ。それができるのが極小の待庵。『ユリシーズ』の1日や、第17挿話で列挙される細部に似たものを感じた。任意の水素原子がどこから来たか、第17挿話調に列挙して行けば、宇宙の始まりに辿り着けるのだろう。流石にそれはやり過ぎだし、専門知識も求められるので、小説でやらないだけで、『ユリシーズ』がやっているのはそういうことだと思った。
📝メモ
●ブルームとスティーヴンが立ちションした後に握手するけど、2人とも手を洗ってないよね?
第18挿話:ペネロペイア
妻モリ―の内的独白。性的な内容が多く、猥褻本として発禁処分を受ける一因になったらしい。でも表現は婉曲的だし、現代の感覚では発禁は過剰だと思う。キリスト教的価値観も影響しているかも?
意識の流れを表現した文体は、ピリオド、カンマに加え、省略形を作るアポストロフィーもない単語の羅列。活字だとめちゃくちゃ読みにくいが、オーディブルだと文の切れ目が分かりやすくて、ただの普通の文章だった。
意識の流れと言っても、フレーズや文ごとに切れ目はある訳で、ピリオド等を無くしたから意識の流れになる、という論理は破綻している。前作『若い芸術家の肖像』からお馴染みの自由間接話法で、登場人物の声を100%にすれば、それが意識の流れだと思う。
『ユリシーズ』は文学の限界に挑戦した。その挑戦は評価されるべきだけど、今回の文体は失敗していると思う。でもそのお陰で活字の限界が分かった。それは文学にとって収穫だったと思う。
前回の羅列の文体は『イリアス』の戦力の羅列をオマージュしていたと思う。それを受けての今回、意識の流れという表現方法が最も活きるのは活字ではなく朗読だと思った。『ユリシーズ』は最終的に口承文学に回帰して幕を下ろしている?そしてまた新しい一日が始まる。
全体の総括
全体の感想
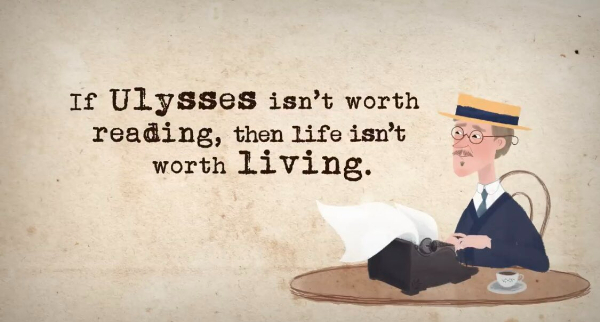
全体の感想。シンプルに疲れた。これは小説ではなくて大説だ。大谷さんが小谷さんだったら違和感あるのと同じ理屈で🤣
「ユリシーズに読む価値がないなら、人生に生きる価値はない」
→これには賛同。理由は以下。
内容:まず反戦(無条件に賛同)。そして平凡な日常(ユリシーズは楽しもうと思って読まないと楽しめない。人生も同じ)。
文体:文学の限界への挑戦。挑戦が否定される人生なんか生きる価値ない。
※fun(楽しい)ではなくworth(価値がある)な点に要注意。funではないがworthということもあるから。お互いの意見が衝突してたら、片方又は双方が言葉の意味を曲解している可能性がある。お互いにどう定義、解釈してるかを確認して擦り合わせたら、合意できることも多いかも?知らんけど。
『ユリシーズ』に読む価値はあると思うけど、自分の好みには合わなかった。嫌いとまでは言わないけど、好きではない。楽しめたのは一部で、総合的には苦痛だったから。前作『若い芸術家の肖像』は好き。
📝ユリシーズの英語の難易度
私史上最高を更新。理解できないところ多数。翻訳者さん凄い。1ページ当たりの未知の単語数や理解不能な文法数が一線を超えると心が折れる。初心者時代を思い出した。今初心者の人の気持ちを想像した。人の気持ちは分からないけど、想像力は失わないようにしたい。
ちなみに、英語の難易度次点はスコット・フィッツジェラルドの『楽園のこちら側』です。
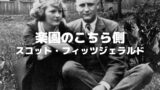
ジェイムズ・ジョイスとの会話
読後のフォローアップで、本書を読んでみた(アイルランド出身の批評家でジョイスのパリ時代の友人でもある筆者が、ジョイスとの会話を記録した本)。
ジョイスの小説に対する考え方やシェイクスピア、プルースト、エリオット、ジッド、スタンダール、ロシアの作家達など、様々な作家に対する考え方が窺い知れてとても興味深く読んだ。
ジョイスは常識の逆を行きたがる作家。小説の常識がプロットを求めるなら、プロットのない作品く。「古代は善、中世は悪」が常識なら、中世的な作品を書く。小説はこうあるべきという手枷足枷から小説を解放した。何を書くかではなく、どう書くか。現代作家はデンジャラスに書かなければならない。
『ユリシーズ』を音楽でイメージすると、ストラヴィンスキーの『春の祭典』なのかもしれない。『春の祭典』を始めて聴いて意味不明だった感覚は、『ユリシーズ』の読後感に似ている。『春の祭典』はその後ライブで聴いて大好きになった。『ユリシーズ』もそうなるといいな。
ユリシーズは基本的にユーモラスな作品とのこと。第一挿話はそう思ったけど、その後は難解さに負けて楽しめなかった。再読時に意識したい。別の本(風の影)にこう書いてあった「本は自分を映す鏡。自分の中にあるものが見えるだけ」その本が合わなかったら、自分に足りないものがあると考えたい。
史上最高の文学作品とは?
『ユリシーズ』の、20世紀最高の英語小説、世界文学史上最高傑作の一つ、みたいな評価は、文学にとってどうなんだろう?
難解な作品もあっていいと思うけど、『ユリシーズ』は難解すぎて限度を超えている。文学初心者が読んで、苦痛を味わい、でもそんな作品が文学史上最高レベルの評価を得ていたら、文学を嫌いになってしまうかも?
ただでさえ斜陽の出版業界、文学の顔的な位置に『ユリシーズ』を置いておくことはプラスよりマイナスが大きくないか?
文学は誰の為のもの?少なくとも教授達の為のものではないと思う。作家の為でもないと思う。読者の為、より良い世界を作る為のものだと思う。
文学の顔的な位置に並べる作品としては、人間が描けている、美しい文章、緻密な構成、ページを捲らせる力、限度を超えない難易度、普遍性、公益性など、総合的に得点が高い作品が相応しいと思う。
『ユリシーズ』はストレートではなく変化球、しかも極端な変化球だから、せめてトップ10圏外、最高でも11位くらいにしておくのが、文学の今後の発展の為に良い気がした。
結局、世界文学史上最高傑作は何だろう?各評価項目で軒並み高得点を獲得しているだけじゃなく、文学の顔としての公益性も特に重視することとして、トルストイの『戦争と平和』に一票を入れたい。
読書好きの人達が選ぶ世界文学史上最高傑作も色々聞いてみたい。
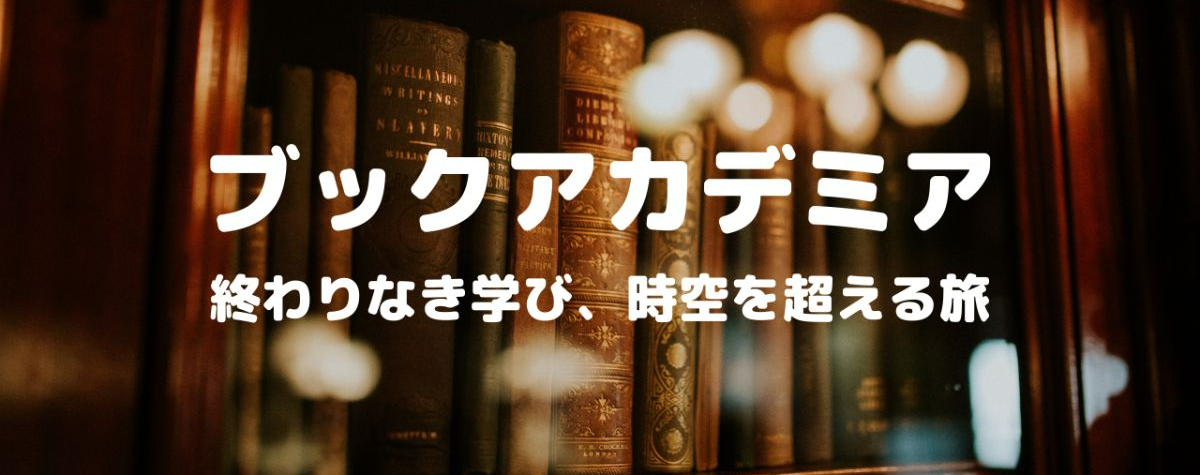

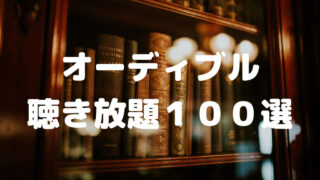
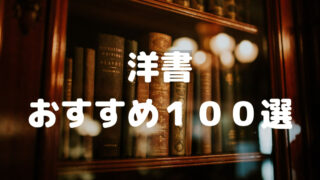
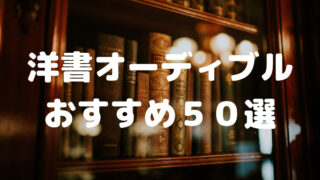





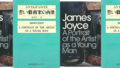
コメント